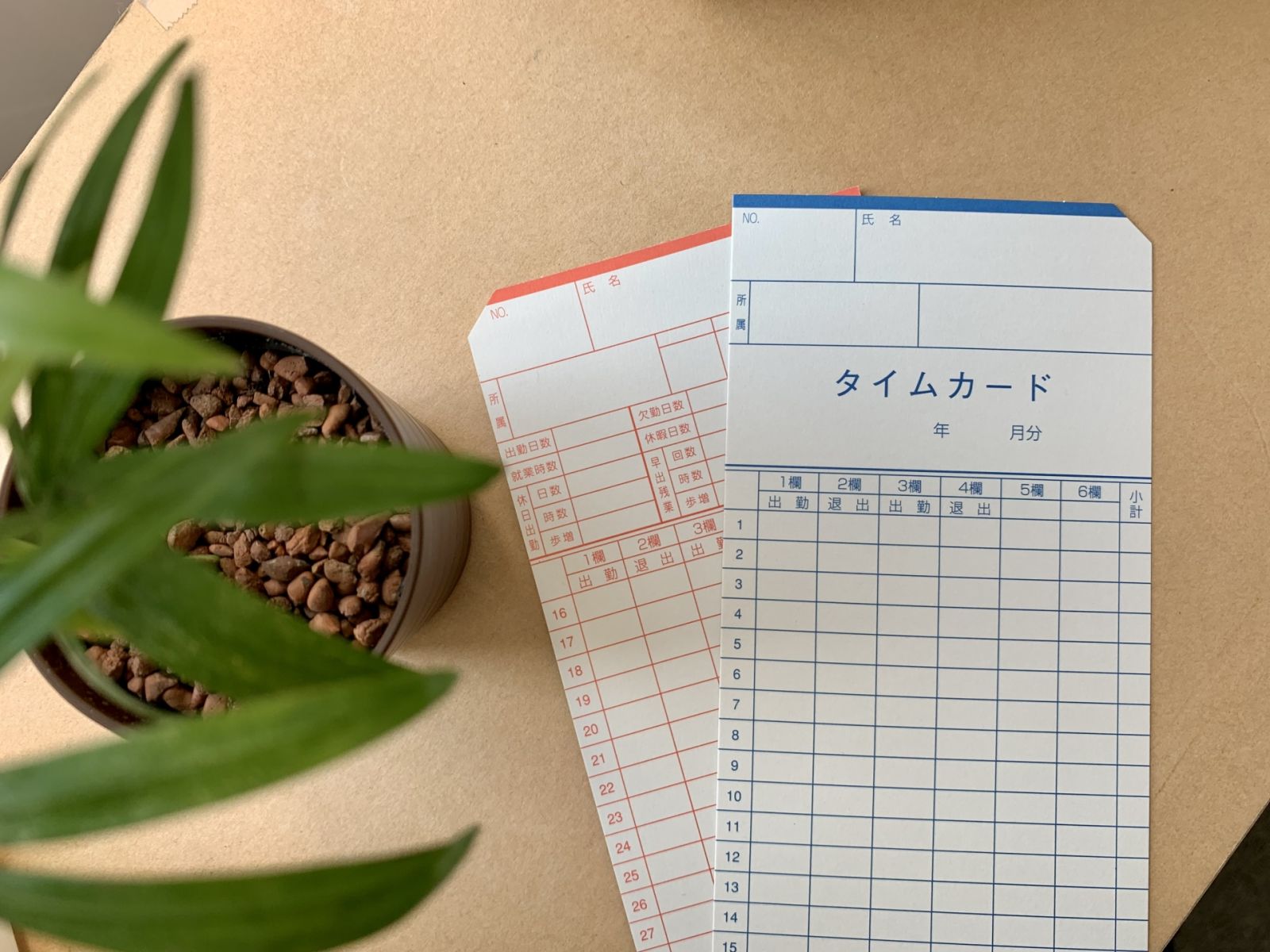コラム
労働基準法で連続勤務は何日まで可能? 2026年からは14日以上は禁止?
2025.04.09

連続勤務が可能な日数は、労働基準法によって定められています。しかし、現行の法制度では2週間以上の連続勤務などで労働者の負担が大きくなるケースがあるため、議論の対象となっています。2026年の法改正に向けて提言されている内容は、13日を超える連続勤務をさせないようにすることです。この記事では、現行制度における連続勤務の最大日数や、2026年の労働基準法改正で検討されている内容について解説します。
労働基準法で定められた連続勤務日数
まずは、労働基準法で定められた連続勤務日数について確認しましょう。労働基準法では、原則として規定されている連続勤務日数と、変形休日制における連続勤務日数に違いがあります。詳しい内容は以下の通りです。
労働基準法での規定
現行の労働基準法では、休日に関する内容として以下のように定められています。
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法第三十五条第一項では、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないことが原則として定められています。この決まりに従って休日を設ける場合、連続勤務日数は最大で12日間です。1週間の起算日は、就業規則で定められている場合はその曜日、定められていない場合は日曜日となります。
例えば、1週目の日曜日を休日として、月曜日から土曜日までの6日間出勤した場合、連続勤務日数は6日間です。続けて2週目の日曜日から金曜日までの6日間も出勤し、最終日となる土曜日を休日にすると、1週目の月曜日から2週目の金曜日までの12日間連続で勤務することになります。
このケースでは、前述した毎週少なくとも1回の休日が設けられているため、現行の労働基準法で許可される範囲内です。また、1週間の起算日が日曜日以外に設定されている場合も同様に、最大で12日間までの連続勤務が認められます。
変形休日制における連続勤務日数
変形休日制とは、4週間に4日以上の休日を設ける制度です。業務上の都合で週休1日を取ることが難しい場合を考慮した例外的なルールとして、変形休日制が定められています。前述の労働基準法第三十五条第二項にもとづき、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については、必ずしも週1回の休日を付与しなくても問題ありません。
そのため、現行の変形休日制においては、連続勤務の最大日数が24日間となります。例えば、4週間の内の最初または最後の4日間に休日をまとめたり、最初の2日間と最後の2日間を休日にしたりすると、残りの24日間は連続で出勤日とすることが可能です。
ただし、変形休日制を導入するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、就業規則に変形休日制を導入する旨と、変形休日制の起算日を記載することが求められます。また、制度の導入後に従業員からの反発を招かないように、丁寧に説明した上で合意を取ることも重要です。
連続勤務日数に違反した場合の罰則
労働基準法で認められる最大日数を超えて連続勤務が発生した疑いがある場合、まず労働基準監督署による調査が実施されます。調査の結果、労働基準法への違反が認められると是正勧告や指導の対象となり、企業は速やかに対応する必要があります。
労働基準法で、連続勤務日数に違反した場合の罰則を定めた規定は以下の通りです。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
上記の内、連続勤務に関する内容や第三十五条に該当するため、適切な対応が行われなかった場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられる可能性があります。
労働基準法の規定は、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどすべての雇用形態が適用の対象です。そのため、連続勤務日数の上限を超えた出勤が発生しないように、適切な管理を行う必要があります。
現行の労働基準法の問題点
現行の労働基準法の問題点として、4週4休の変形休日制では理論上最長で48日間の連続勤務が可能となってしまうことが挙げられます。例えば、4週間の最初の4日を休日として24日間連続で出勤日としたあとに、次の4週間では最後の4日間を休日に設定すると、48日間の連続勤務が可能です。
しかし、48日間もの長期にわたる連続勤務は、労働者の心身の負担の観点から現実的ではありません。この問題を解決するための方法として、労働基準法の改正に向けた議論の中で14日以上の連続勤務の禁止が検討されています。
2026年の労働基準法改正で連続勤務はどう変わる
2026年の労働基準法改正はまだ決定事項ではなく、専門家による提言や議論が行われている段階です。しかし、現在検討されている内容を把握しておくことで、実際に改正が行われた場合に向けた準備や対策を進めやすくなります。
ここでは、2026年の法改正に向けて提言されている内容や、連続勤務日数を変更する目的、法改正で予想される労働者や企業への影響について解説します。
2026年の法改正に向けての提言内容
2025年1月に公表された「労働基準関係法制研究会報告書」によると、4週4休で長時間の連続勤務が生じても、労働基準法違反には該当しないことが懸念されているポイントです。労働者の権利を守るという労働基準法の本来の趣旨に沿うための方法として、2週2休とするなど連続勤務日数の上限をできるだけ減らすような措置が提言されています。
また、法定時間を超えた労働が可能となる「36協定」に休日労働の条項を設けて、割増賃金を支払えば理論上は無制限に連続勤務が可能になることも、報告書で言及されている懸念点です。労使協定を結ぶ場合であっても、過度な連続勤務は健康上望ましくないため、制限が必要ではないかという旨が述べられています。具体的には、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」といった規定を労働基準法上に設けることが、報告書内で提言されている内容です。この提言とともに、災害復旧などのやむを得ない状況や、顧客・従業員の安全上必要な場合などを考慮した代替措置の必要性についても述べられています。
連続勤務日数を変更する目的
連続勤務日数の変更が提言されている主な目的は、過労死や過労自殺の防止、ワークライフバランスの改善などです。労働基準関係法制研究会の報告書では、労災保険における精神障害の認定基準として2週間以上にわたる連続勤務が、心理的な負荷がかかる事例となっている点に言及されています。この基準をふまえて、労働者の心身の健康を守るために、2週間以上の連続勤務を防ぐことが提案されました。
厚生労働省が発表する「令和6年版過労死等防止対策白書」によると、業務における心理的負荷で精神障害を発病したとする労災請求件数は近年増加傾向です。2023年度の労災請求件数は3,575件で、前年度と比べて892件の増加となっています。また、職業別自殺者数の年次推移データによると、2023年度の有職者の自殺者数は8,858人で、前年より282人増加しています。これらの状況を改善し、過労による健康への悪影響や自殺を防止することが、連続勤務日数を変更する目的です。連続勤務できる最大日数を現在よりも減らすことで、労働者がワークライフバランスを保ちやすくすることが期待されています。
法改正で予想される影響
労働基準法が改正された場合の影響として、メリットとデメリットの両方が予想されます。まず、企業と労働者の両方にとってのメリットは、労働環境や健康状態の改善です。連続勤務日数が制限されれば、過剰な労働を防ぎ、心身の健康を保ちやすくなります。休息を適切に取れるようになると、業務への集中力やモチベーションが向上し、生産性が高まることも想定されるポジティブな影響です。
一方で、連続勤務日数が現在より少なく制限される労働者側のデメリットとして、収入が減少する可能性が挙げられます。特に、非正規社員など時間給の雇用形態で働く従業員の場合は、労働日数が減ることで収入が減るリスクがあります。
また、法改正で予想される企業側へのネガティブな影響は、人手不足の悪化です。慢性的な人材不足により長期間の連続勤務が常態化している企業では、法改正によって十分な人員の割り当てが難しくなる可能性があります。特に、輸送や医療などは人材不足による悪影響が特に懸念される業界です。連続勤務の最大日数が13日間までに制限された場合に備えて、業務の効率化や追加の人材募集などの対策を進める必要があります。
これらの良い影響と悪い影響の両方をふまえて、労働環境を改善するための法改正が進められていくでしょう。
まとめ
現行の労働基準法における連続勤務日数の制限や問題点、2026年の法改正に向けて検討されている内容などについて解説しました。現在の法制度で指摘されている課題は、2週間以上の連続勤務が可能なことです。この課題を解決するために、2026年の法改正では連続勤務の上限が13日以内に制限される可能性があります。企業は適切なシフト管理や労働時間の最適化を行い、労働者が健康的に働ける環境を整えることが重要です。