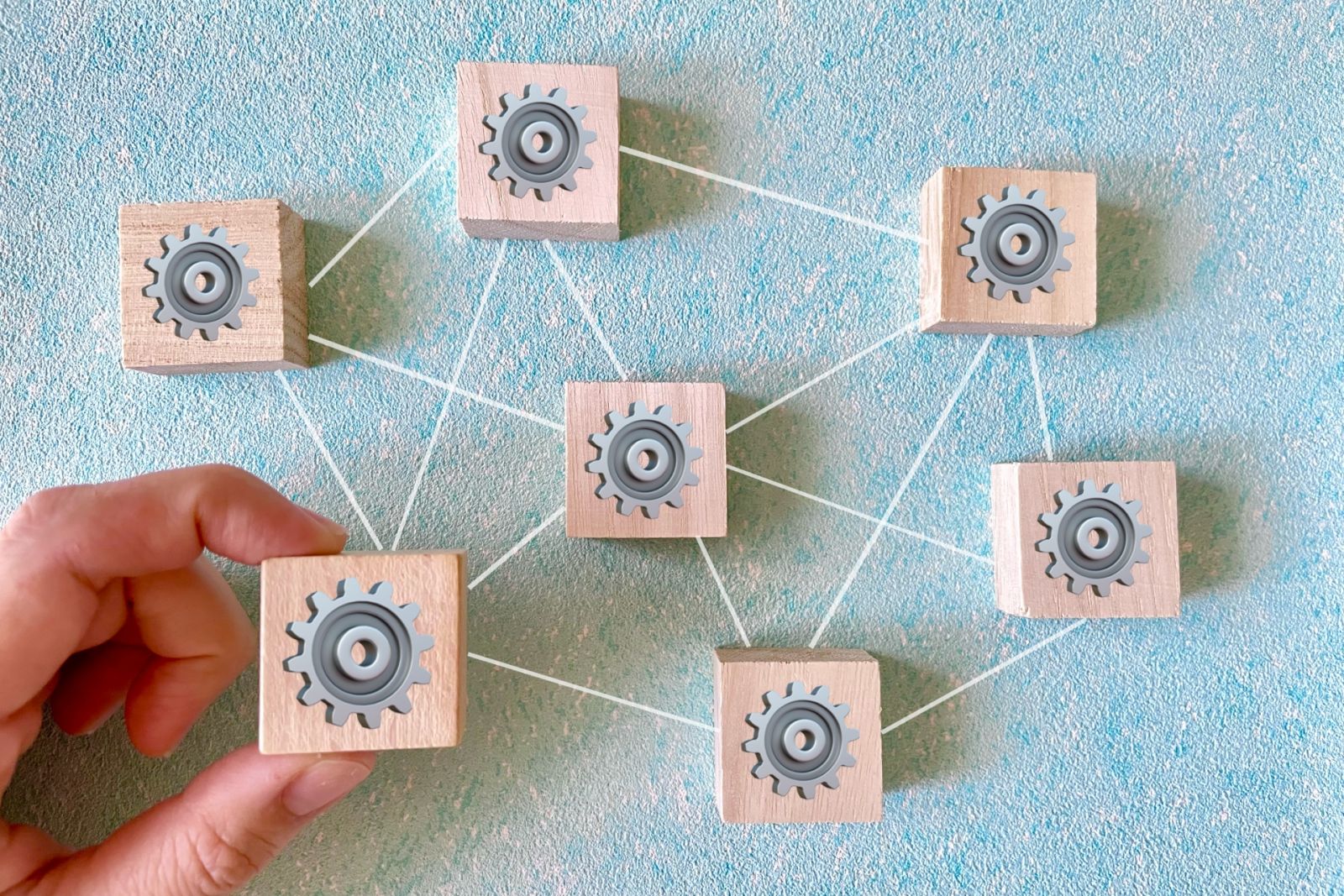コラム
103万円の壁がなくなる? これまでの制度と緩和によるメリットとは
2025.04.09

パートやアルバイトなどで働いている人のなかには、103万円の壁を超えないように仕事を調整している人もいるでしょう。2024年にはこの「103万円の壁の引上げ」が大きな話題となり、今後の動向が注目されています。この記事では103万円の壁の概要や緩和によるメリット、緩和に向けた動きなどについて解説します。現状の制度を正しく理解し、今後の動向に注目していきましょう。
※本記事の内容は2025年4月時点の情報に基づいています。最新の情報は、ご自身でご確認ください。
103万円の壁とは
「103万円の壁」とは、所得税の支払いが発生するかどうかのボーダーラインのことを意味します。所得税における基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円の合計額が103万円で、収入が非課税として扱われる控除の範囲内に収まります。そのため、パートやアルバイトなどで得た給与所得が年間で103万円以下の場合は、所得税の支払いが不要になるという仕組みです。
所得税とは、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得に課せられる税金のことを意味します。所得税は給与所得に対して課税されるため、給与所得とは別に扱われる通勤手当や出張に伴う交通費などは除外して考えます。
103万円の壁を超えた場合に起こること
103万円の壁を超えた場合は、「所得税・住民税が発生または増加する」「親の税負担が増加する(親の扶養に入っている場合)」「配偶者の税負担が増加する(夫や妻の扶養に入っている場合)」の3つの変化が起こります。それぞれについて解説します。
所得税・住民税が発生または増加する
給与所得が年間103万円を超えると、所得税と住民税の支払いが発生、または増加することになります。まず、給与所得が年間103万円を超えた場合は、所得税を納付しなければなりません。
住民税は、年収100万円を超えたあたりから支払いが発生、または増加します。住民税は、居住する都道府県や市区町村などの自治体に納める税金で、自治体の条例や財政状況などによって追加徴収をしたり減税されたりする場合があります。
住民税には「所得割」と「均等割」の2種類があり、パート収入が100万円以下でほかに所得がない場合、住民税(所得割)はかかりません。しかし、パート収入が100万円以下でも、居住する市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合があるため注意しましょう。
親の税負担が増加する(親の扶養に入っている場合)
親の扶養親族となっている場合、アルバイトの年収が103万円を超えると扶養控除が適用されなくなり、親の税負担が増加します。子どもが扶養親族となって扶養控除が適用される場合、控除額は子どもの年齢によって異なります。この場合の子どもの年齢とは、計算する年の12月31日時点の年齢です。年齢ごとの控除額は、次の通りです。
- 16歳以上の場合は「一般の控除対象親族」となり、控除額は38万円
- 19歳以上23歳未満の場合は「特定扶養親族」となり、扶養額は63万円
子どもが扶養親族となるかどうかで、親の税負担に大きな差が出ます。子どもがアルバイトをする際には、扶養内でするかどうかについて十分に検討することが大切です。
配偶者の税負担が増加する(夫や妻の扶養に入っている場合)
夫や妻の扶養に入っている場合、年収が103万円を超えると配偶者控除が適用されなくなるため、配偶者の税負担が増加します。ただし、年収103万円から201.6万円未満の場合は配偶者特別控除が適用されるため、年収が103万円を超えたからといってすぐに控除が受けられなくなるわけではありません。
配偶者特別控除は年収が上がるにつれて控除額が減額しますが、年収103万円から150万円未満の場合は配偶者控除と同じ控除額です。年収150万円を超えると段階的に控除額が減額していくため、その分配偶者の税負担も増加していきます。
出典:国税庁「家族と税」
103万円の壁の問題点
所得税・住民税の負担軽減のためや、扶養控除・配偶者控除が適用されるために103万円の壁を超えないようにすることで、「働ける時間を抑える必要があり、世帯収入も増加しない」「働き控えによって企業が人手不足に陥る恐れがある」という問題点が生じる恐れがあります。それぞれの問題点について解説します。
働ける時間を抑える必要があり、世帯収入も増加しない
年収を103万円未満に抑えるためには、パートやアルバイトで働く時間を調整する必要があります。年収103万円を超えないためには働ける日数や時間を制限しなければならないため、「勤務時間が短い」「勤務時間の融通が利く」などの条件で求人を見つけなければなりません。条件に合った求人がなければ、働きたくても働けない期間が増えてしまうでしょう。
また、せっかく勤務先が決まったとしても、年収103万円を超えないようにシフトを調整しなければならないため注意が必要です。年収の上限が決まっていると、世帯収入の増加も難しくなります。
働き控えによって企業が人手不足に陥る恐れがある
103万円の壁を超えないように従業員が仕事をセーブしてしまうと、企業が人手不足に陥る恐れがあります。総務省の調査によると、少子高齢化の進行により、日本の生産年齢人口(15歳から64歳)は1995年をピークに減少しており、今後も減少傾向が続くと見込まれています。生産年齢人口の減少は労働力人口の減少にもつながり、企業にとっても人手不足の問題が深刻化してしまうでしょう。
そこでさらに103万円の壁を超えないように仕事をセーブする人が増えると、ますます労働力の減少の問題が加速してしまいます。
出典:総務省「令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少」
103万円の壁がなくなるのはいつから?
103万円の壁がなくなる件については、2025年2月時点では具体的な内容については未確定の段階です。ここでは現段階での引き上げ時期や金額などについて解説するほか、103万円の壁が引き上げられることによるメリットについても解説します。
2025年1月から160万円に引き上げる方針を提案
2024年12月20日に、自民・公明両党は令和7年の税制改正大綱を決定し、年収103万円の壁について、123万円に引き上げる方針を示しました。しかし、2025年2月18日に、新たに160万円程度に引き上げるという方針が提案されています。
非課税枠は年収に応じて変わり、年収200万円以下の人は所得税の非課税枠を160万円に、年収200万円から500万円以下の人は2年間の限定措置としてさらに10万円を上乗せするとされています。
一方で、年収500万円を超える人はさらなる上乗せはありません。そのため、年収が低い人ほど非課税枠の引き上げ幅を大きくするという内容になっています。
この件については2025年の通常国会で審議され、2025年の所得から適用されて2025年分の年末調整などで対応される予定です。(※2025年2月現在)
103万円の壁が160万円の壁になることによるメリット
103万円の壁が160万円の壁になることで、これまで年収を103万円未満に抑えるために仕事をセーブしていた人たちが現状よりも働く時間を増やせるようになります。働く時間を増やせれば手取り収入の増加が期待でき、さらに国民の労働意欲の向上が期待できるでしょう。
課税されない所得の上限が引き上げられることで、税負担を気にせずに働くことが可能になり、世帯全体の収入の増加も見込めるといえます。さらに、手取りが増えることは消費生活の活性化にもつながるでしょう。
また、働き控えによる人手不足も解消されることが期待できます。近年は賃上げが進んでいることで時給が上がっていても、103万円の壁のために仕事をセーブせざるを得ない人も多いでしょう。しかし、上限が引き上げられることで仕事をセーブする必要がなくなれば、その分パートやアルバイトなどの労働力の増加が期待できます。
その他の「年収の壁」
103万円の壁以外にも、「年収の壁」と呼ばれるものにはいくつか種類があります。ここでは「106万円の壁」と「130万円の壁」についてそれぞれ解説します。
106万円の壁
106万円の壁とは、従業員が51人以上の規模の企業において週20時間以上働いた場合、社会保険への加入義務が発生するボーダーラインです。この場合は月収8万8000円以上、年収106万円を超えると社会保険への加入する必要があり、保険料の支払いが発生します。
しかし、厚生労働省は2024年12月10日に106万円の壁の撤廃案を審議会の部会に示し、了承を得ました。この案では、賃金の要件を撤廃することとし、時期は2026年10月と想定されています。
130万円の壁
130万円の壁とは、社会保険に加入する義務が発生するボーダーラインです。従業員が50人以下の企業などで働く場合でも、年収が130万円を超えると扶養を外れることになります。130万円を超えて働く場合は勤務先の厚生年金に加入し、国民年金保険料も自分で納める必要があります。
まとめ
103万円の壁は、所得税の支払いが発生するかどうかのボーダーラインです。103万円を超えると所得税の支払いが発生し、親や配偶者の税負担も増えるため、年収を103万円未満に抑えるために仕事をセーブしていた人も多いでしょう。
103万円の壁の上限が引き上げられることで働き控えが緩和され、企業の人手不足の解消にもつながることが期待されます。
JOEでは、給与計算を合理化・効率化できる給与計算システムを提供しています。Web給与明細機能も備えており、企業の給与規程に合わせてフレキシブルに計算式が構築可能です。企業独自の特別手当や各種控除、複雑な計算ロジックにも柔軟に対応可能で、給与計算業務の効率化を実現します。
サービスの詳細は「給与計算システム(Web明細含む)」のページをご覧ください。