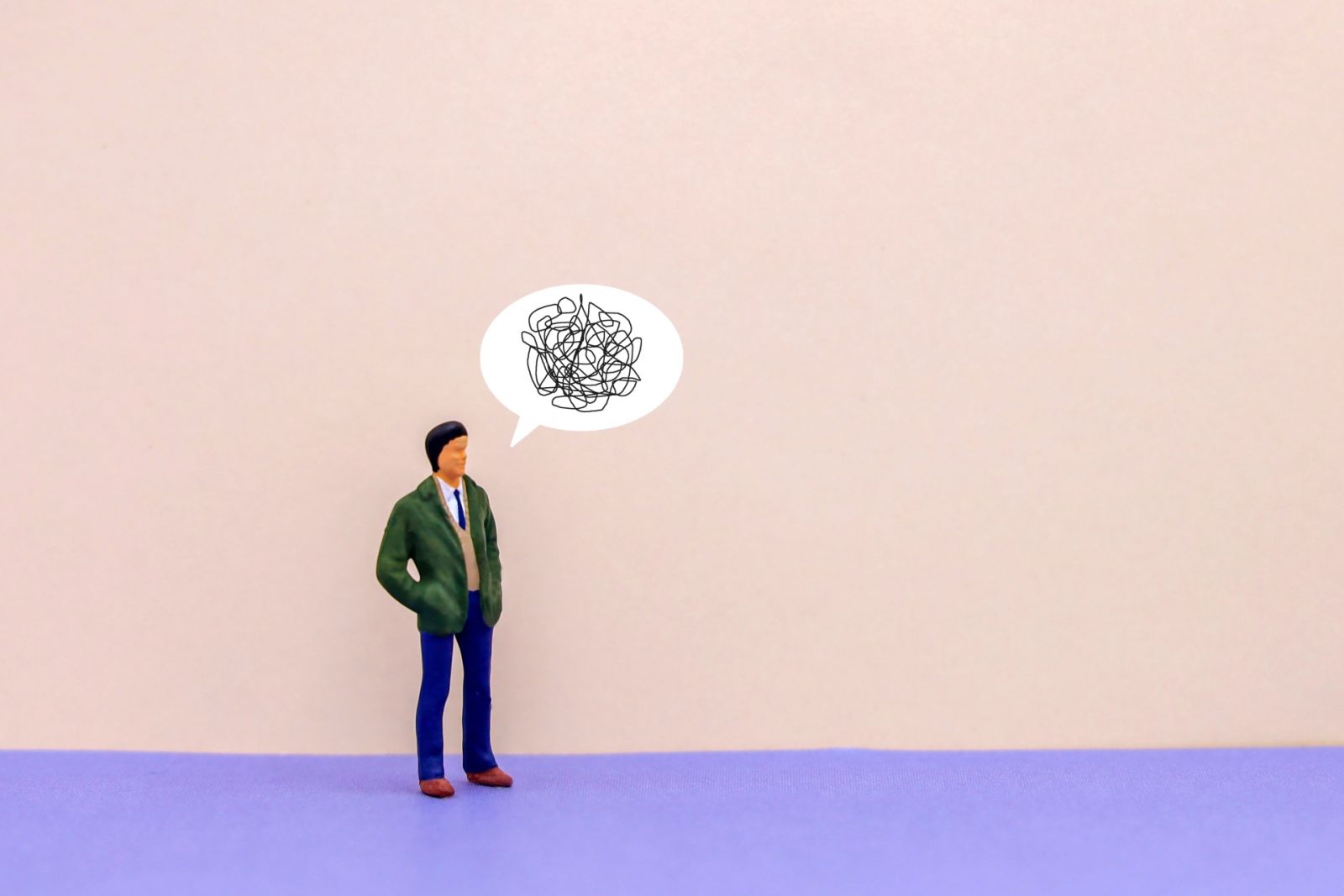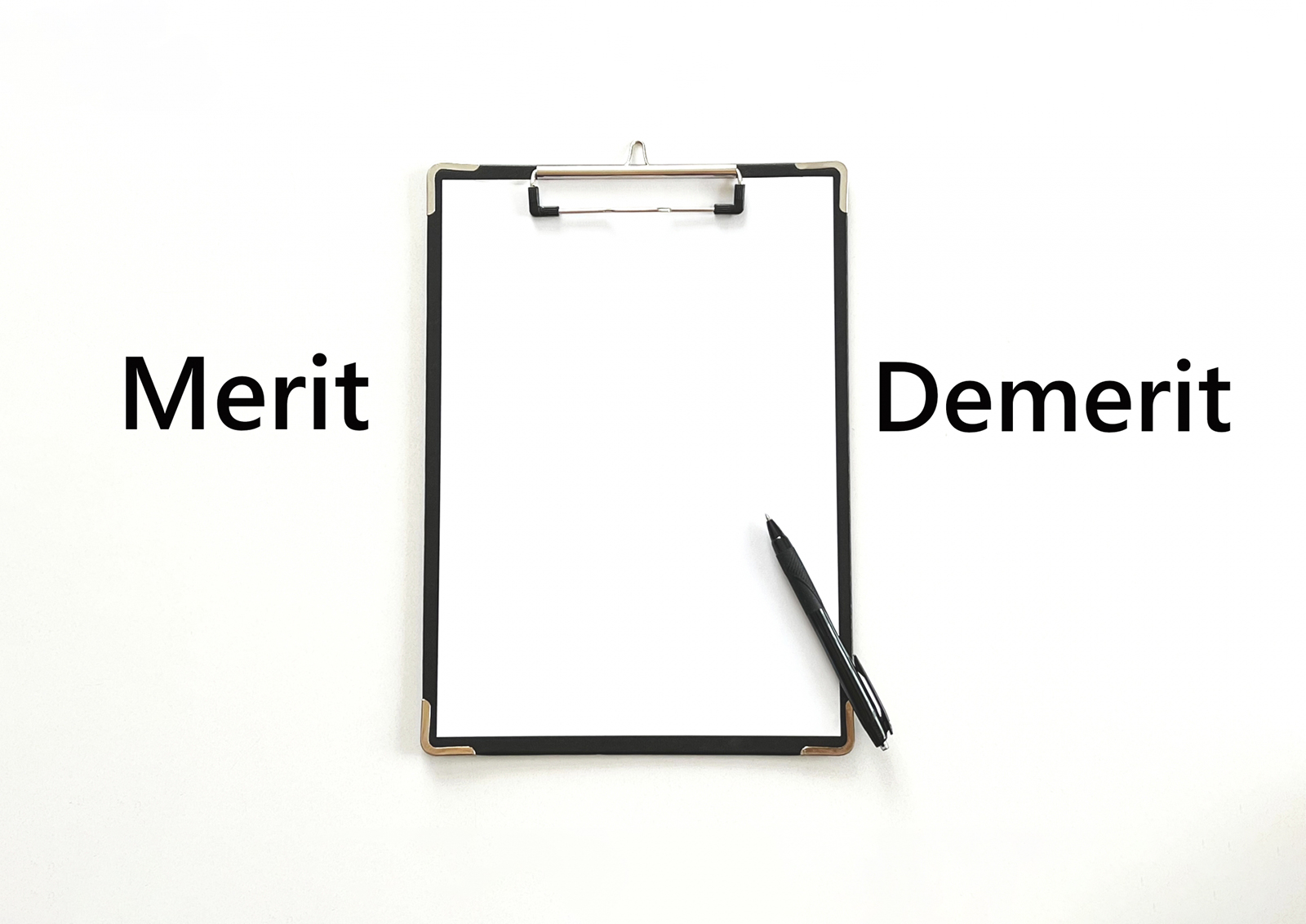コラム
育休手当における手取り10 割の条件は? いつから対象?
2025.04.09

出産後は何かとお金がかかる時期でもあり、収入が減少してしまうことが育休取得の大きなハードルになっていたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。男性の育休取得の推進の一環として、2025年4月1日より育休手当(育児休業給付金)に加えて「出生後休業支援給付金」が導入され、一定の条件を満たすことで手取り相当額が10割程度となる制度改正が行われます。この記事では、育休手当(育児休業給付金)で手取り10割になる条件や支給条件、計算式などについて解説します。受給の際の注意点も解説するので、育休手当についての理解を深める際に役立ててください。
育休手当(育児休業給付金)とは
育休手当とは、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者に対して支給される手当で、正式名称を「育児休業給付金」といいます。まずは育休手当の概要について、「受給資格」と「支給要件」のそれぞれに分けて説明します。
受給資格
育休手当(育児休業給付金)の受給資格は、1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)と定められています。
ただし、いわゆる「パパ・ママ育休プラス」の制度を利用する場合は1歳2か月、保育所待機などの事情がある場合は1歳6か月または2歳に達する前までとなります。また、育休取得中に退職する場合は対象外です。
有期雇用労働者の場合は、養育する子が1歳6か月、保育所待機などの事情がある場合は2歳に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでない場合は支給対象になります。
支給要件
育休手当の(育児休業給付金)支給要件は、次の通りです。
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
- 一支給単位期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること
【2025年4月〜】育休手当の手取りが10割に
2025年4月から導入される「出生後休業支援給付金」により、一定期間の育児休業給付金が「実質手取り10割」となる仕組みが整備されます。ここでは「給付率の変更点」「手取り10割相当となる期間」「手取り10割相当となる要件」についてそれぞれ解説します。
給付率の変更点
育休手当(育児休業給付金)の給付率は休業開始時賃金日額の67%で、社会保険料が免除されることを考慮すると、実質的な手取りは8割程度となります。そこに、2025年4月から導入される「出生後休業支援給付金」の要件を満たすことで、さらに賃金の13%が上乗せされることになるため、実質的に10割相当の手取りとなる仕組みです。
手取り額が10割程度に引き上がることにより、特に男性社員の育休取得がしやすくなるため、夫婦間の育児分担が進むと言われています。
手取り10割相当となる期間
手取りが10割相当になるのは、夫婦そろって14日以上の育休を取得した場合に最大28日間となります。対象となるのは、男性の場合は子の生後8週間以内、女性の場合は産後休業後8週間以内に育休を取得した場合になります。
手取り10割相当となる要件
手取りが10割相当となるのは、雇用保険被保険者で、夫婦そろって14日以上の育休を取得した場合です。フリーランスや自営業など、雇用保険の被保険者でない場合は対象外となります。
ただし、次のように配偶者の育児休業を要件としないケースもあります。
- 配偶者がいない場合
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない場合
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中の場合
- 配偶者が無業者の場合
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない場合
- 配偶者が産後休業中の場合
- 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない場合
上記の場合は夫婦そろって育児休業を取得するという要件は必要なく、本人のみの育休取得で受給が可能になります。
育休手当の計算方法と計算例
ここでは育休手当(育児休業給付金)と出生後休業支援給付金の計算方法と計算例についてそれぞれ解説します。
計算方法
育休手当(育児休業給付金)の支給額は、「休業開始時賃金日額支給日額67%(181日目以降は50%)」の計算式で算出します。ここでいう休業開始前賃金日額とは、休業開始前の6か月間の総支給額を180日で割った金額です。
さらに、出生後休業支援給付金の支給額は、「休業開始時賃金日額支給日数(上限28日)13%」の計算式で算出します。
支給額は上記の合計で「育児休業給付金+出生後休業支援給付金」となります。これらの給付金は非課税で、社会保険料も免除となるため、手取り額が実質約100%となる仕組みです。
ただし、支給金額には上限があるため、一定以上の収入がある場合は実質的な手取り額が10割に満たないケースもあります。
計算例
ここでは月給30万円の従業員が28日間休業した場合の計算例を解説します。
1:「休業開始前賃金日額」を算出する
休業開始前賃金日額は休業開始前の6か月間の総支給額を180日で割った金額なので、「月給30万円6か月÷180日=1万円」となります。
2:育休手当(育児休業給付金)の支給額を算出する
育休手当(育児休業給付金)は「休業開始時賃金日額支給日額67%(181日目以降は50%)」で算出するので、「1万円28日67%=18万7,600円」となります。
3:出生後休業支援給付金の支給額を算出する
出生後休業支援給付金の支給額は「休業開始時賃金日額支給日数(上限28日)13%」で算出するので、「1万円28日13%=3万6,400円」となります。
4:支給金額を算出する
支給金額は「育児休業給付金+出生後休業支援給付金」となるため、「18万7,600円+3万6,400円=22万4,000円」となります。
育休手当を受給する際のポイント・注意点
育休手当を受給する際には、「育休手当は社会保険料の免除がある」「一定の条件を満たして育休を延長する場合、育休手当の支給も延長される」「育休手当の上限額に注意する」の3つの点について注意しましょう。それぞれについて解説します。
育休手当は社会保険料の免除がある
産前産後休業中と育児休業中は、社会保険料が被保険者、事業主ともに免除されます。社会保険料とは、健康保険料と厚生年金保険料のことです。通常は給与から社会保険料が差し引かれますが、育休手当の場合は社会保険料が差し引かれることはありません。
ただし、住民税については注意が必要です。住民税は前年度の所得に基づいて課税されるため、前年に所得がある場合は育児休業中でも住民税の支払い義務は発生します。一方で、出産手当金や育児休業給付金、出生後休業支援給付金は非課税となるため、それらを受け取っても翌年の住民税には影響しません。
一定の条件を満たして育休を延長する場合、育休手当の支給も延長される
育児休業の期間は一定の条件を満たす場合に延長することが可能で、その際は育休手当(育児休業給付金)の支給も延長されます。具体的には、「子どもが1歳から1歳6か月までの延長」「1歳6か月から2歳までの再延長」が認められます。
育児休業の期間が延長されるのは、次の①と②の要件を満たす場合です。
- 育児休業の申出に係る子について、市町村に対して保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳また1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
- 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳または1歳6か月に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定であった方が、以下のいずれかに該当した場合。
- 死亡したとき
- 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
- 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
- 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間または産前休業期間及び産後休業期間)
ただし、①については児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる「無認可保育施設」は含まれません。
また、あらかじめ子どもが1歳または1歳6か月に達する日の翌日に保育所等における保育が実施されるように申込みを行っていない場合など、復職の意思がない場合は延長は認められません。
育休手当の上限額に注意する
育休手当には上限額があるため、休業開始前に一定以上の収入があった場合は手取り相当額が10割に満たない場合もあります。
令和7年7月31日までの支給上限額は、次の通りです。
休業開始時賃金日額の上限額:15,690円
休業開始時賃金日額の下限額:2,869円
支給日数が30日の場合の支給上限額と支給下限額は、次の通りです。
【給付率67%の場合】
支給上限額:315,369円
支給下限額:57,666円
【給付率50%の場合】
支給上限額:235,350円
支給下限額:43,035円
また、出生後休業支援給付金については、支給日数が28日の場合の支給上限額と支給下限額は次の通りです。
支給上限額:57,111円
支給下限額:10,443円
まとめ
2025年4月に出生後休業支援給付金の制度が導入されることで、夫婦そろって14日以上の育休を取得した場合に最大28日間、手取り相当額が10割程度となります。この制度を活用することで、とくに男性が育児休業を取得しやすくなることが期待できます。
JOEでは、「人事給与業務アウトソーシング(BPO)」「給与計算システム(Web明細含む)」「人事管理システム・申請ワークフロー」「勤怠管理システム」「年末調整Web申告システム」など、豊富なサービスをご提供しております。詳細は「サービス一覧」のページをご覧ください。