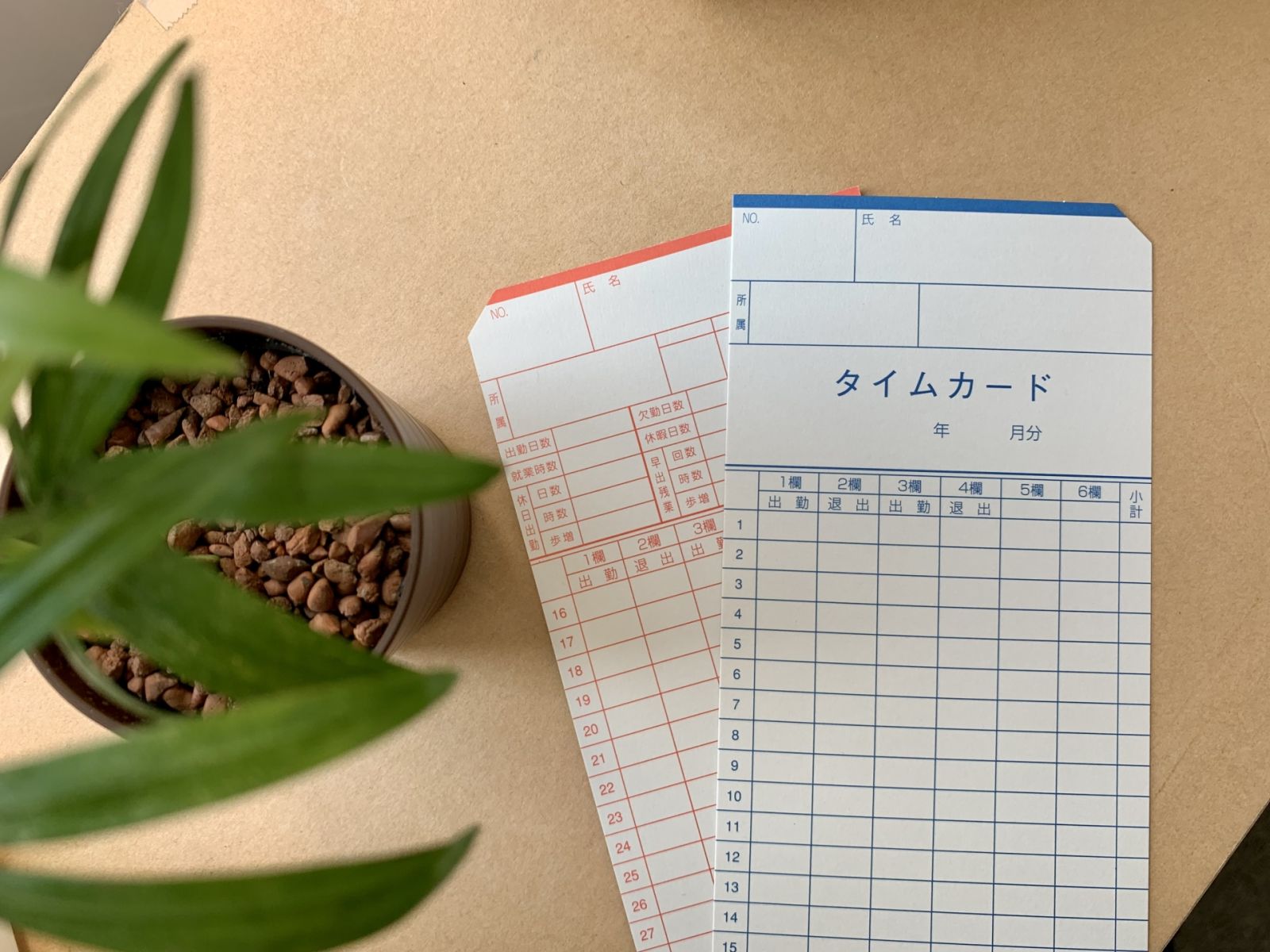コラム
労働基準法における休憩時間で15分単位が有効なケースとは
2025.04.09

労働基準法には休憩時間についてのルールが定められており、使用者はルールに則って労働者へ休憩を付与しなければなりません。この記事では、労働基準法における休憩時間の基本ルールや、15分単位での付与が有効な場合について説明します。休憩時間を与える際の注意点も解説するので、健全な労働環境づくりに役立ててください。
労働基準法における休憩時間の基本ルール
休憩時間に関するルールは、労働基準法第34条に定められています。まずは規定されている休憩時間の基本的なルールについて説明します。
出典:労働基準法
労働時間が6時間以下の場合
労働時間が6時間以下の場合は、使用者は労働者に対して休憩時間を付与する必要はありません。ただし、6時間を1分でも超える場合は、45分以上の休憩時間が必要になります。
労働時間が6時間を超える場合
労働時間が6時間を超え、8時間以内の場合は、使用者は労働者に対して45分以上の休憩を付与しなければなりません。法律上では最低でも45分の休憩が必要ですが、45分以上の休憩を付与しても問題ありません。
労働時間が8時間を超える場合
労働時間が8時間を超える場合は、使用者は労働者に対して60分以上の休憩を付与しなければなりません。この場合も法律上では最低でも60分の休憩が必要ですが、60分以上の休憩を付与しても問題ありません。
違反した場合の罰則
労働基準法に定められた休憩に関するルールに違反した場合は、使用者に対して「30万円以下の罰金」または「6か月以下の懲役」が科されます。実際に違反してしまった場合は、罰則が科せられるだけでなく社会的信用を失ってしまうことにもつながってしまいます。使用者と労働者の双方がルールを正しく理解し、遵守していくことが大切です。
たとえば労働者側が「休憩時間はいらないからその分早く帰りたい」「休憩時間の分も働いて給料を増やしたい」などと申し出たとしても、6時間以上勤務する労働者には必ず休憩時間を与えなければなりません。労働者からの申し出であっても、労働基準法に違反することのないように気をつけましょう。
また、休憩時間を付与する際には、残業時間も考慮する必要があります。たとえば7時間30分勤務で45分の休憩時間が付与されている場合、1時間の残業をすると8時間30分勤務したことになるため、労働基準法のルールでは60分以上の休憩時間が必要になります。
この場合、あらかじめ残業を見込んで就業規則を見直し、7時間30分勤務の場合でも休憩時間を60分とすれば、残業をしたとしても休憩時間に関しては労働基準法上の問題はありません。ただし、法的な問題がないからといって、残業を前提に業務をさせることのないようにしましょう。
休憩時間を与える際の注意点
休憩時間を与える際には、次の5つの点について注意しなければなりません。それぞれについて解説します。
労働時間の途中に設ける
労働基準法第34条には、休憩時間について「労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。つまり、始業前や終業後に休憩時間を与えるのはルール違反になります。
始業前や終業後に休憩時間を与えたとしても、そもそも勤務時間外となるため、休憩時間としての意味がありません。たとえば8時間勤務で60分の休憩時間が付与されている労働者が「終業1時間前に休憩時間をとって早く退社したい」と申し出たとしても、ルール違反になってしまうため実現不可能です。
また、45分の休憩時間を付与されている労働者が急な残業によって8時間を超えて労働する場合は、15分の休憩時間を追加する必要があります。その際も労働時間の途中に休憩時間を設けなければならないため、適切なタイミングで休憩時間を与えるようにしましょう。
原則として一斉に付与する
労働基準法第34条には、休憩時間について「一斉に与えなければならない」と定められています。ただし、「労働者の過半数で組織する労働組合」や「労働者の過半数を代表する者」との間に書面による協定がある場合は、休憩時間を一斉に与えなくてもよいケースもあります。
また、労働基準法施行規則第31条において定められた業種では、休憩時間をずらすことが可能です。たとえば病院や飲食店、宿泊施設などで従業員が同時に休憩してしまうと不都合が生じてしまいます。そのため、そのような業種では一斉付与の原則が適用外となります。
一斉付与の原則が適用外になる業種には、運輸交通業や商業、旅館・飲食業、金融・広告業、映画・演劇業、保健衛生業などがあります。
出典:労働基準法施行規則
休憩時間を自由に利用させる
労働基準法第34条には、休憩時間について「自由に利用させなければならない」と定められています。休憩時間中は労働者を業務から解放しなければならず、基本的には労働者の行動について干渉することはできません。
休憩時間は労働者が自由に利用できる時間であるため、使用者が労働者に対して休憩時間に業務に関することを命じるのはルール違反となります。
たとえば休憩時間中の電話番や来客対応、ランチミーティングへの出席などは業務から完全に離れているとはいえないため、労働時間とみなされるでしょう。その場合は、別の時間帯に休憩時間を与えなければなりません。また、当直や宿直勤務における仮眠時間も、緊急事態などの発生時にはすぐに対応する必要があるため、基本的には休憩時間ではなく労働時間として扱われます。
雇用形態を問わず同じ基準で付与する
労働基準法で定められた休憩時間に関する規定は、雇用形態を問わずすべての労働者に該当します。正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなどの労働者にも同じように適用されなければなりません。
「パートやアルバイトは6時間以上勤務した場合も休憩時間がない」「正社員とアルバイトでは同じ労働時間でも付与される休憩時間が異なる」など、雇用形態によって休憩時間の付与に差があるのはルール違反です。どのような雇用形態であっても、労働基準法の基本ルールに則って等しく休憩時間が付与される必要があります。
ただし、労働基準法上の「管理監督者」に該当する立場の場合は、労働時間や休憩時間に関する規定が適用されません。
手待ち時間は休憩時間に含まれない
休憩時間中は労働者を業務から解放し、労働者の自由な時間としなければならないため、「手持ち時間」とみなされる待機時間については労働時間として扱われます。手持ち時間とは、「業務に備えて待機している時間」「使用者の指示があればすぐに対応できるように待機している時間」などの状況です。
具体的には、来客対応や電話番のために待機する時間、タクシードライバーや配送業者、医療従事者などの待機時間などが該当します。このような状況にある時間は使用者の指揮命令下にあると考えられるため、基本的には休憩時間ではなく労働時間として扱われます。
休憩時間は分割して与えることも可能
労働基準法で義務付けられている休憩時間は、業務形態に合わせて分割して付与することも可能です。休憩時間を昼休みとして付与するのが一般的ですが、一括付与が難しい業務形態の場合などは、手持ち時間に該当しない範囲内で分割して自由に付与できます。
たとえば45分間の休憩時間を15分単位で分割することは、法律上は特に問題ありません。とはいえ、あまりにも休憩時間を細かく分割すると食事を十分にとれなかったり心身が休まらなかったりするため、あくまでも社会通念上休憩として機能する範囲で分割する必要があります。
ここでは休憩時間を分割して与えることが有効なケースと有効ではないケースについて、それぞれ解説します。
休憩時間で15分単位が有効なケース
休憩時間を15分単位に分割する場合、たとえば45分の休憩時間を「30分+15分」のように分割して与えることは問題ありません。また、60分の休憩時間を「30分+30分」に分割するのはもちろん、「30分+15分+15分」のように分割することも可能です。
分割した休憩時間を始業前や終業後に充てる場合はルール違反ですが、労働時間の途中にすべて組み込むことが可能であれば問題ありません。
休憩時間で15分単位が有効ではないケース
休憩時間を15分単位で分割した際に、分割した休憩時間の一部またはすべてを始業前や終業後に充てる場合は、ルール違反となります。たとえば45分間の休憩時間を「労働時間の途中に30分+仕事が終わった後に15分」と分割するのは法律上認められません。休憩時間はあくまでも労働時間の途中に付与するものなので、分割したとしても必ずすべての休憩時間を労働時間の途中に設けるようにしましょう。
まとめ
労働基準法に定められたルールとして、労働時間が6時間を超え、8時間以内の場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間が必要です。休憩時間は分割して付与することも可能ですが、あまりにも細かく分割しすぎると休憩時間として機能しなくなってしまうため注意が必要です。
15分単位で分割する場合は、分割した休憩時間は始業前や終業後ではなく、すべて労働時間の途中に設けなければなりません。
休憩時間の扱いをはじめ、勤怠管理でお悩みではありませんか。JOEの勤怠管理システムは、シンプルで分かりやすい画面設計でどなたでも簡単に操作ができ、勤務時間と休憩時間の正確な把握と管理が可能です。導入後のアフターサポートも充実しており、専門知識を持つスタッフが法改正や就業規則の変更にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。詳細は「勤怠管理システム」のページをご確認ください。