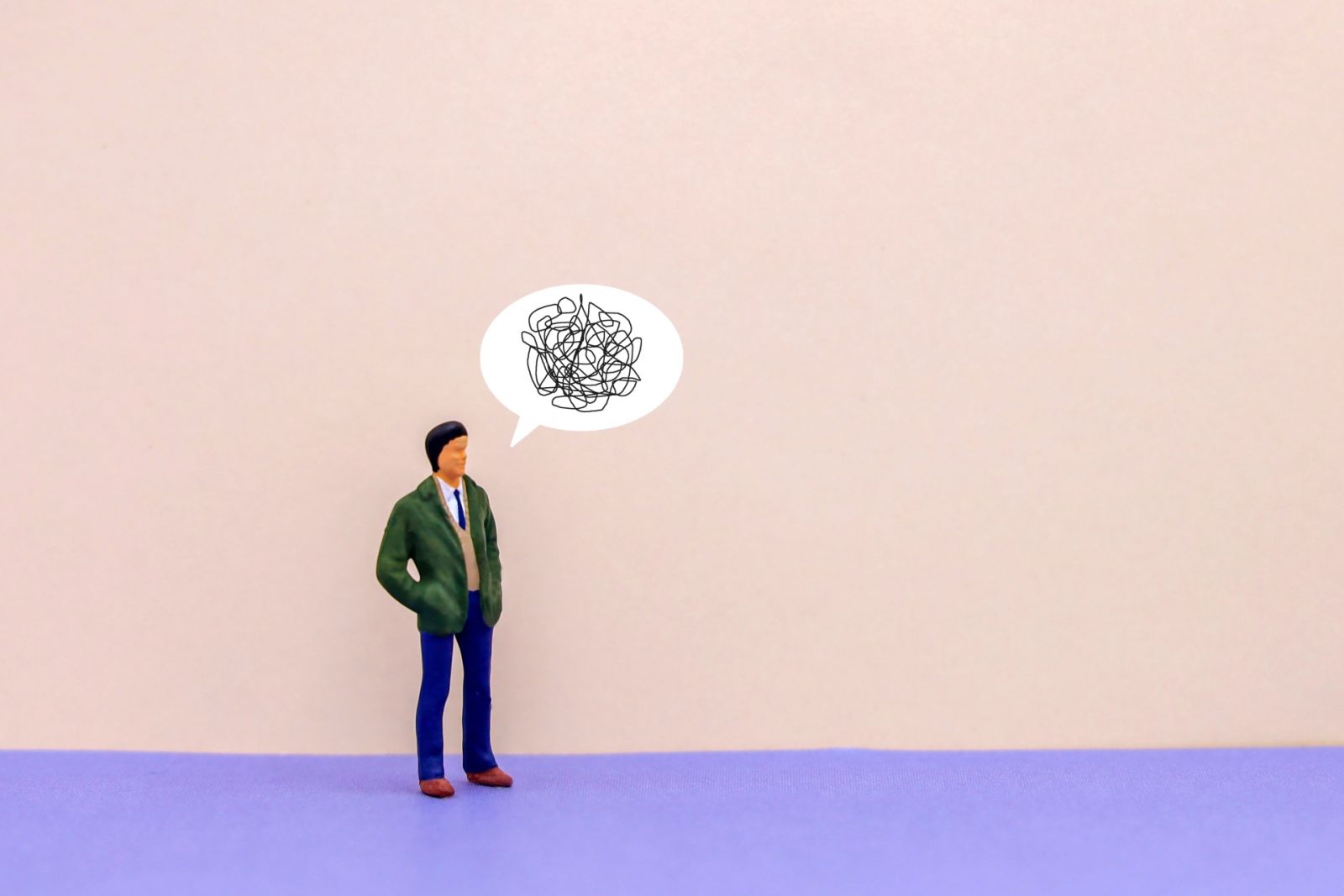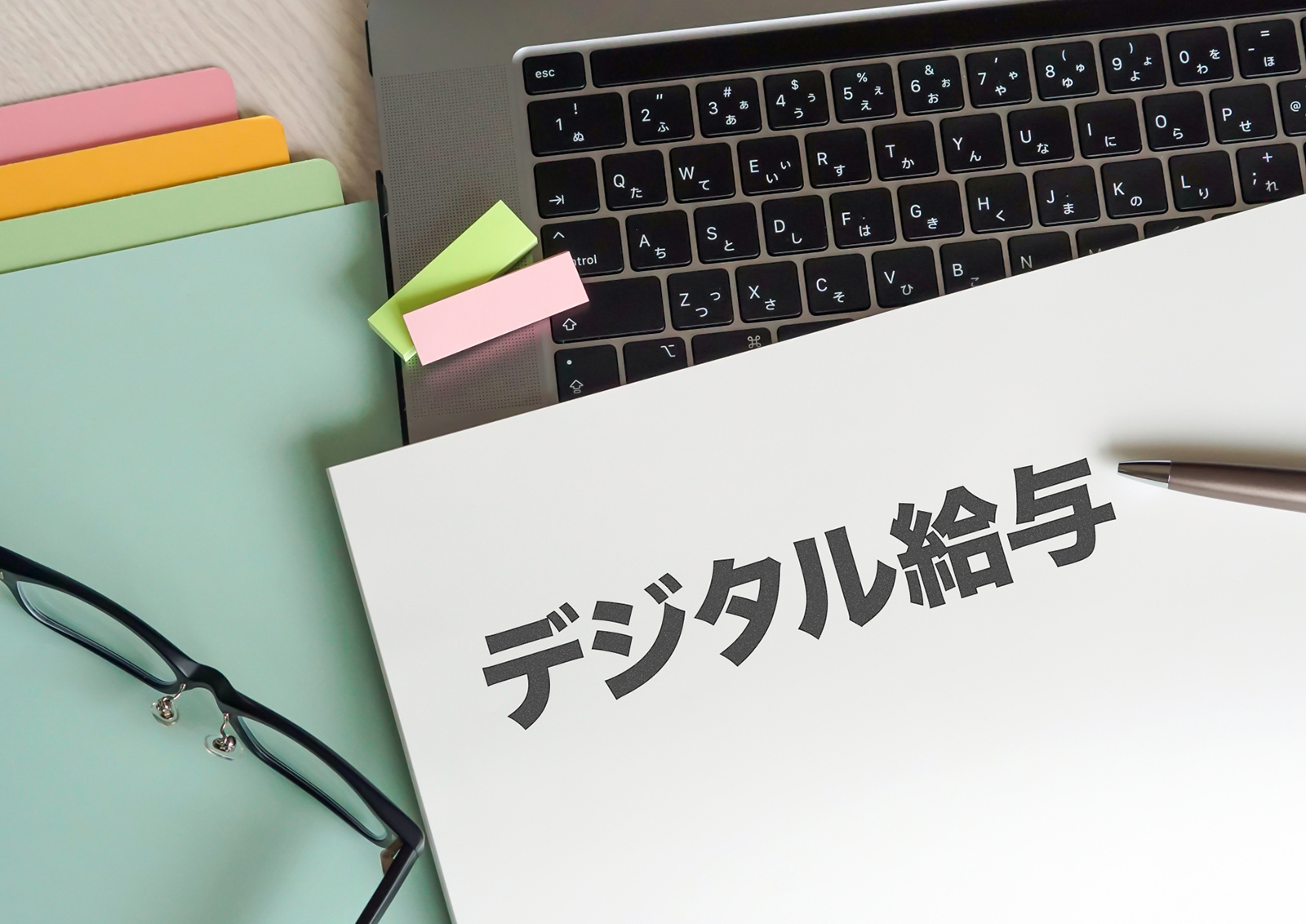コラム
特別徴収税額通知書の仕組みを徹底解説!労務担当者必見
2024.09.18

事業者にとって特別徴収税額通知書は、従業員の個人住民税を給与から天引きしたり、従業員に配布したりするために必要な書類です。月々の徴収税額や徴収期間など、処理に必要な情報が細かく記載されています。本記事では、労務担当者が知っておきたい特別徴収税額通知書の仕組みを解説します。令和6年度より可能になった、特別徴収税額通知書の電子データでの受け取りについての概要や対応策についても併せてお伝えします。
特別徴収税額通知書の基本
まず、特別徴収税額通知書の概念や役割、発行対象者について解説します。全体像を掴み、通知書の意義や価値を確認しておきましょう。
特別徴収税額通知書とは
特別徴収税額通知書は、決定された住民税額を知らせる書類です。地方税法第321条の4および第321条の5に基づいて発行されており、市区町村が毎年5月頃、事業者(特別徴収義務者)に送付します。
市町村が送付する書類は「特別徴収義務者用(会社用)」と「納税義務者用(従業員用)」の、2種類あります。書類には以下の情報が記載されているので、確認しましょう。
- 従業員の氏名と住所
- 課税年度
- 年間の住民税額
- 月々の徴収税額
- 徴収期間
企業は、届いた特別徴収税額通知書に基づいて、従業員の給与から住民税を徴収する義務があります。徴収した住民税は、翌月10日までに市区町村へ納付しなければなりません。また、納税義務者用は従業員に配布します。
特別徴収や通知書の役割と重要性
特別徴収は、従業員に代わって税金を納付する大切な仕組みであり、特別徴収税額通知書は、納付する税額を明確にするという役割があります。
企業は従業員の住民税額を正確に把握しておかなければ、給与の天引きができません。毎月給与から天引きする住民税の根拠として、特別徴収税額通知書を用います。従業員としては、住民税の計算の根拠や、給与から引かれる住民税額を事前に把握できる重要な書類です。必ず5月末頃に特別徴収税額通知書を配布して、確認してもらいましょう。
行政にとって特別徴収制度は、一人ひとりから住民税を徴収する必要がなくなる制度です。本来であれば各人に確定申告をしてもらい、その数字を根拠に住民税を算出して、納付します。それが特別徴収制度では、企業がまとめて従業員から住民税を徴収することにより、従業員ごとの手間をかけることなく税金の徴収が可能となっています。企業としては手間が大きいですが、従業員に特別徴収税額通知書を電子データで配布できるようになるなど、負担を減らす施策も進んでいます。
通知書の発行対象とその理由
特別徴収税額通知書は、「特別徴収義務者用(会社用)」と「納税義務者用(従業員用)」の2種類が企業に発行されます。「納税義務者用(従業員用)」は、企業が従業員に配布します。企業、そして住民税を給与から天引きされる従業員の両方に通知されることで、お互いに住民税額課税内容や徴収額を明確にできる安心感があります。
特別徴収税額通知書の発行の流れ
特別徴収税額通知書はどのような手順で発行されるのか、流れを見ていきましょう。実務上の注意点や、よくあるトラブルと対処法についてもお伝えしていきます。
発行手順と内容
特別徴収税額通知書の発行に関するおおまかな流れは下記の通りです。
- 1月31日までに、事業者は給与支払報告書を市区町村に提出する
- 市区町村は毎年5月頃、特別徴収義務者用(会社用)と納税義務者用(従業員用)の2種類の通知書を、電子データ、もしくは書面にて事業者に送付する。
- 納税義務者用(従業員用)を、企業から従業員へ配布する
会社用の通知書には、従業員全体の住民税情報が一覧化されています。一方で、従業員用に配布する通知書は前年の所得額や各種控除額、納税額などが詳細に記載されています。
実務上の注意点
労務担当が特別徴収税額通知書を取り扱う際は、正確性、速やかな対応、法令遵守などが求められます。特別徴収税額通知書は従業員の住民税に直接関わる重要書類であり、その管理や運用に誤りがあると、従業員の給与や市区町村への納税に影響を及ぼしてしまいます。
従業員に入社、退社、転勤などの異動がある場合は、「給与所得者異動届出書」を提出します。納税者が自ら支払う普通徴収から特別徴収へ変更する場合や、特別徴収から普通徴収へ切り替える場合も書類提出が必要です。常時、従業員の最新情報を更新して、正しく税金が支払えるようにしておきましょう。
発行における、よくあるトラブルとその対処法
特別徴収税額通知書の対応過程では、通知書の未着・紛失や記載内容の誤りといったトラブルが発生することもあるかもしれません。
もし、特別徴収税額通知書が未着または紛失した場合は、市区町村の税務課に連絡をして再発行してもらえるか確認しましょう。電子データで受け取る場合で、eLTAX(エルタックス)でのダウンロードに必要な保護番号通知メールが届かない、紛失したという場合も、市区町村に問い合わせます。なおデータは、通知が行われた日から60日間、照会・ダウンロードが可能です。
特別徴収税額通知書に記載されている従業員の情報や税額に誤りがある場合は、速やかに市区町村の税務課に連絡し、修正を依頼しましょう。必要に応じて、給与支払報告書の内容を確認し、訂正が必要な場合は訂正届を提出します。
あらかじめトラブルを最小限に抑えるために、よくあるトラブルと対処法を押さえておきましょう。
特別徴収税額通知書の電子化とは

令和6年度より、eLTAX(地方税ポータルシステム)で、特別徴収税額通知書の電子データ(正本)での受け取りが可能になりました。紙の通知書と比べて、未着または紛失のリスクが軽減し、従業員一人ひとりに配布する手間や書類保管の場所がいらなくなるなどのメリットがあります。業務効率の向上、コスト削減、環境負荷の軽減などにつながるでしょう。
一方で、個人情報を含む重要なデータを扱うため、適切なシステム導入やセキュリティ対策、法的要件の遵守など、新たな課題にも対応が必要です。
労務担当者の対応策
特別徴収税額通知書を受け取る労務担当者が、取り扱いにおいて知っておきたい対策方法をお伝えします。
正確な処理方法
労務担当者が特別徴収税額通知書を正確に処理するためには、システムの利用方法を含む最新の知識の把握とチェック体制の構築が不可欠です。入社、退職、休職、転職などのタイミングでの取り扱い方も十分に把握しておく必要があります。
特別徴収税額通知書の処理は、従業員の給与計算や納税に直接影響を与える重要な業務です。もし、誤りがあれば、従業員の信頼を損ねたり、法的問題を引き起こしたりする可能性があります。
正確な処理を行うためにも、定期的な研修や勉強会に参加し、労務関連法の最新知識を常に更新してスキルアップを図りましょう。また、個人の経験や勘に頼らずに一定の品質を保った処理ができるように業務手順書を作成し、標準化された処理を行うことも大切です。
ミスやエラーの防止策
特別徴収税額通知書の処理におけるミスやエラーを防止するためには、チェック体制の構築、自動化の活用、定期的な監査が重要です。企業の信頼性を損なわないためにも、ミスやエラーを未然に防ぐ体制を整えることは、労務管理の質を高めることにつながります。
- ミスやエラーの防止策としては以下のようなものが挙げられます。
- チェックリストを作成し、漏れがないか確認する
- システムを導入し、人為的ミスを減らす
- 定期的に処理内容の精査をする
- エラー発生時の報告・対応フローを明確にし、労務担当者へ周知徹底する
- 過去のエラー事例を分析し、再発防止策を講じる
ミスやエラーを完全に防ぐことはできませんが、手作業をやめて自動化をし、チェック体制を整えていきましょう。
eLTAXについて疑問やトラブルなどがあった際は、「特別徴収税額決定通知書(電子)についてのよくあるご質問」(地方税共同機構)のページも確認してみると良いでしょう。
特別徴収税額通知書の電子化における対応
特別徴収税額通知書の電子化に対応するためには、電子システムの操作習得、セキュリティ強化、データ管理体制の確立、従業員への説明、既存フローからの移行期間中の柔軟な対応が重要です。
電子化に伴い労務担当者も業務に支障をきたさないように、移行期間中に電子システムの操作方法を習得し、対応マニュアルを作成しましょう。また、電子化の対応は納税者である従業員にも関わってきます。今まで紙で受け取っていた通知書を電子データで受け取り可能になったことや保管方法などの説明をしっかりと行わなければ、従業員の理解や協力を得ることはできません。
スムーズに対応するためにも、しっかりと準備をしておきましょう。
特別徴収税額通知書の仕組みを理解し、正確で効率的な処理を行おう
特別徴収税額通知書は、企業が従業員の住民税を給与から徴収するための重要な書類です。市区町村が発行し、企業と従業員に送付されます。令和6年度から始まったeLTAXで特別徴収税額通知書の電子データ受け取りが可能になったことにより、今後さらに電子化に伴う業務効率向上やコスト削減が期待できます。特別徴収税額通知書の仕組みと対応策を理解し、正確な処理を行い、電子化への適切な対応をしていきましょう。
法改正、特別徴収税額通知書の電子化など、毎年のように新しくなる仕組みに対応していくのは、労務担当者にとって大きな負担です。そういった負担を軽減し、コア業務に専念できるよう、アウトソーシングを活用する方法も検討してみてはいかがでしょうか。
JOEのアウトソーシングサービスでは、あらかじめ業務内容について十分なヒアリング、業務フローや業務ルールを整理した上で、正確な人事給与業務を可能としています。電子化に伴ってより重要となっているセキュリティ対策の強化策としても有効です。
また、JOEの給与計算システムをお使いいただくことでも、給与計算の合理化、効率化が可能です。複雑な計算式でもシステムに実装させ、負担を大きく軽減させることができます。
サービスの詳細は、「給与計算システム(Web明細含む)」や「人事給与業務アウトソーシング(BPO)」のページからご確認いただけます。